京都の瓦屋根におすすめの耐震補強とは?地震対策の基本を解説
2025/11/26
地震に備えて住まいの安全を見直す際、「瓦屋根は大丈夫だろうか?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
特に京都は、古くからの瓦屋根の建物が多く、伝統的な町家や木造住宅も数多く残されています。風情ある街並みを守る一方で、地震時の屋根の落下や崩壊といったリスクも無視できません。
この記事では、以下の内容について詳しく解説していきます。
・瓦屋根が地震に弱いと言われる理由と構造的な特徴
・京都の瓦屋根に適した耐震補強方法とは?
・補強工事の流れや注意点、費用感
・専門業者に依頼する際のポイント
屋根の点検や耐震対策を検討している方にとって、判断の材料となるよう、専門的な視点を交えて丁寧に解説します。
瓦屋根はなぜ地震に弱いと言われるのか?

重量のある構造が揺れに弱い
瓦屋根の最大の特徴は「重量」です。一般的な和瓦は、1㎡あたり約40kgもの重さがあるとされ、屋根全体では1トンを超えることもあります。
この重量が建物上部に集中していると、地震の揺れによって建物が不安定になりやすく、結果として「倒壊リスク」が高まるとされているのです。
また、揺れによって瓦がズレたり落下したりすることもあり、歩行者や隣家への被害にもつながる可能性があります。
旧来の工法では「固定されていない」瓦も多い
現在主流となっている「防災瓦」は、釘やビスなどでしっかりと固定される仕組みになっています。
しかし、京都市内の築年数が古い住宅では、従来の「土葺き工法(つちぶきこうほう)」が用いられているケースが少なくありません。
この工法では、瓦は土の上に並べているだけで、金具などによる固定がされていないため、地震の振動で一気に崩れ落ちる危険があるのです。
建物自体の耐震性にも影響する
屋根が重ければ重いほど、建物全体の耐震設計にも影響を与えます。
特に柱や梁が傷んでいたり、基礎に不安がある木造住宅では、重たい瓦屋根との組み合わせが致命的な弱点となってしまう場合もあります。
京都の瓦屋根におすすめの耐震補強方法とは?

京都のように歴史的建築が多い地域では、外観の美しさを保ちつつ、屋根の耐震性を高める工法が求められます。ここでは、実際に多くの住宅で採用されている代表的な補強方法をご紹介します。
棟の積み直し(棟瓦の耐震化)
棟(むね)瓦とは、屋根の頂点にある部分で、家全体の「背骨」ともいえる重要な箇所です。昔ながらの土葺きでは、大量の土の上に瓦を積んでいくだけの構造でした。
しかし、現在では「耐震棟工法」や「乾式工法」といった補強技術により、モルタルや土に頼らず金具でしっかり固定する方法が主流になっています。
棟瓦が地震で崩れやすい理由は、「高さと重量」です。積み直し工事では、この棟部分を一度解体し、金具や接着材を併用しながら低重心で再構築します。
特に風圧や地震動の力が集中しやすい棟部をしっかり補強することで、屋根全体の安定性が格段に向上します。
瓦の「緊結工法」への変更
古い瓦屋根では、瓦がただ並べられているだけというケースも少なくありません。これに対して、近年主流になっているのが「緊結工法(きんけつこうほう)」です。
これは、瓦一枚一枚を釘やビス、金具などで下地材にしっかりと固定する方法。ずれや落下のリスクを減らし、地震による被害を最小限にとどめます。
また、軒先やケラバ(屋根の端部)など崩れやすい部分には、特別な「面戸瓦」や「留め金具」を用いてさらに補強します。
緊結工法は、見た目を大きく変えずに安全性を高めることができるため、京都のような景観配慮が求められる地域においても非常に有効なのです。
葺き替えによる軽量化対策
もし屋根の劣化が激しく、瓦の破損や下地の腐食が進んでいる場合は、「部分補修」ではなく屋根全体の葺き替えが必要になることもあります。
このとき、重たい和瓦から軽量な「防災瓦」や「金属屋根材(ガルバリウム鋼板など)」へ変更することで、屋根重量を半分以下に抑えることも可能です。
屋根が軽くなると、建物の揺れ幅が小さくなり、耐震性が飛躍的に向上します。
もちろん「和瓦の雰囲気を残したい」という場合には、外観が瓦に似たデザインの軽量屋根材もありますので、目的や予算に応じて選ぶとよいでしょう。
瓦屋根の耐震工事にかかる費用と工期は?
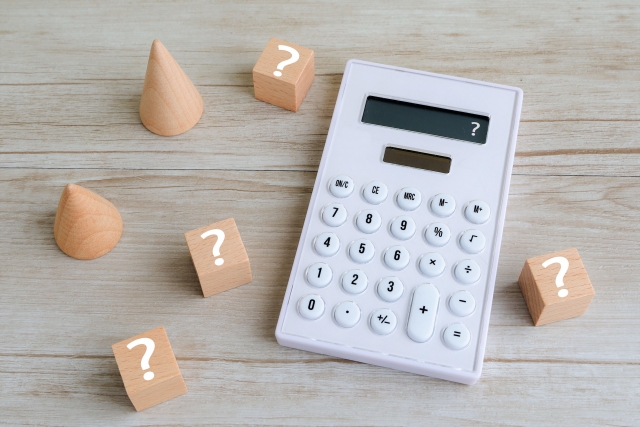
耐震補強工事を検討する際に、多くの方が気になるのが「どれくらいの費用がかかるのか」「どのくらいの期間で終わるのか」といった点ではないでしょうか。ここでは工事の内容別に、費用相場や工期の目安をご紹介します。
工事内容別の費用相場
耐震補強と一口に言っても、その内容によって費用は大きく異なります。以下は主な工事ごとの目安です(住宅の規模や屋根の状態によって変動があります)。
棟の積み直し
棟瓦の高さを抑え、金具や耐震モルタルで固定し直す工事です。
費用相場:10万円〜30万円程度(棟の長さや形状により増減)
瓦の緊結工法(ビス固定)
既存の瓦を一度外し、再利用または交換しながら緊結する方法。
費用相場:30万円〜80万円程度(屋根の面積が大きいほど高額に)
屋根全体の葺き替え(軽量化目的)
重い和瓦から軽量屋根材へ交換するフルリフォーム工事です。
費用相場:80万円〜200万円程度
使用する屋根材(ガルバリウム鋼板、防災瓦、軽量スレートなど)により大きく変わります。
※金額はすべて一般的な木造住宅(2階建て・屋根面積70〜100㎡前後)を想定した目安です。
工期の目安と注意点
工期はおおよそ以下の通りです。
・棟の積み直しのみ:約2〜3日
・緊結工法:約3〜5日
・葺き替え:約1週間〜10日程度
ただし、天候(特に雨天)や足場設置の有無、現地の状況によっては前後することがあります。
とくに梅雨時期や台風シーズンは工事の遅れが出やすいため、事前のスケジュール調整や余裕をもった段取りが大切です。
また、耐震補強を含む工事では「下地(野地板や防水シート)の劣化」が発覚し、追加工事が必要になるケースも少なくありません。
このような場合に備え、予算と工期には多少の余裕を持たせておくと安心です。
火災保険・補助金の活用について
地震による倒壊や風災による瓦の飛散が心配な方にとって、工事費用の負担は少なくありません。
ただし条件を満たせば、火災保険や自治体の耐震補助制度を利用できる場合もあります。
火災保険でカバーできるケース
台風や突風で瓦が飛んだ、棟が崩れたといった場合は、火災保険の「風災補償」で修理費が支払われる可能性があります。
申請には被害箇所の写真や修理見積書が必要となるため、事前に業者へ相談するのが得策です。
★山口板金がおこなった火災保険を活用した施工実績★
▽関連記事
自治体の耐震補助制度
京都市では「木造住宅耐震診断・改修補助制度」が設けられており、昭和56年以前に建てられた住宅を対象に、補強工事への補助金が出ることがあります(要事前申請)【※参考:京都市公式サイト】。
補助金制度は年ごとに内容が変更されることもあるため、最新情報は必ず市区町村の窓口や公式HPで確認しましょう。
★山口板金がおこなった京都市の補助金制度を活用した施工実績★
▽参考記事
京都市で使える屋根修理の補助金は?補助金を活用した施工事例も紹介
耐震補強を依頼する際の注意点

京都で瓦屋根の耐震補強を検討するなら、施工業者選びが結果を大きく左右します。工事の仕上がりや耐久性はもちろん、費用の透明性やアフターフォローまで、信頼できる業者かどうかを見極めることが大切なのです。
信頼できる業者の選び方
まず第一に確認したいのが、その業者が「瓦屋根の施工実績に長けているか」という点です。
瓦屋根の耐震工事は、一般的な屋根リフォームとは異なる専門知識と技術が求められます。たとえば、瓦の固定方法、下地補修の判断、防災瓦の特性理解などは、経験豊富な職人でなければ正しく対応できません。
次のような業者は、信頼性が高いと言えるでしょう。
・地域密着で長年営業している
・瓦屋根の施工事例を写真や説明付きで公開している
・一級建築板金技能士など、屋根工事の有資格者が在籍している
・相談・点検・見積もりが無料で対応可能
・丁寧なヒアリングと提案をしてくれる
また、飛び込み営業や急かす営業には注意が必要です。「すぐに直さないと危険」「今なら特別価格で」といった言葉に惑わされず、複数業者に相談し、冷静に判断することが安心につながります。
見積もり・契約時に確認したいポイント
見積もり書や契約書には、工事内容を細かく明記してもらいましょう。「一式」「補強工事一式」など、内容があいまいな記載には要注意です。
具体的には、以下のような項目を確認してください。
・使用する瓦の種類(例:防災瓦、ガルバリウム鋼板など)
・緊結方法(ビス・ワイヤーなどの固定方法)
・下地補修の有無とその範囲
・足場設置・撤去の費用
・残材や古瓦の処分費
・工期と天候による延長時の対応
また、口約束はトラブルのもとです。必ず書面で残しておくようにしましょう。
無資格施工・格安業者のリスク
価格だけで業者を選ぶのは非常に危険です。
特に「極端に安い見積もり」を出す業者には注意が必要で、以下のようなケースが起こり得ます。
・耐震性能が不十分な簡易施工で済まされる
・使用材料が説明と異なる(安価な代用品に変更)
・工事後すぐに瓦のズレや雨漏りが発生する
・アフター対応が不十分、連絡が取れない
瓦屋根の補強は、建物の命を守る重要な工事です。安かろう悪かろうでは、逆に将来の出費が膨らんでしまいます。
見積もりは「価格」だけでなく、「内容の明確さ」「業者の対応」「施工体制」など、総合的に判断することが必要です。
まとめ
瓦屋根は、日本の伝統建築の象徴とも言える美しさを持ちながら、現代の耐震基準にはそのままでは適合しづらいという一面もあります。
とくに京都のように歴史ある住宅や町並みが残る地域では、見た目を損なわず、確実に耐震性を向上させる工夫が求められるのです。
防災瓦への葺き替え、瓦の緊結、下地の補強など、現代の技術を取り入れた屋根の耐震補強は、「今の暮らし」と「未来の安全」を両立するための選択肢です。
「うちは大丈夫」と思っているうちに、災害は突然やってきます。まずは屋根の状態を正しく知るところから、耐震対策を始めてみませんか?
京都での瓦屋根の補強なら、地域密着で屋根工事を行う【山口板金】までご相談ください。点検・見積もりは無料で対応しております。
Q&A
Q. 瓦屋根の補強工事は何日くらいかかりますか?
A. 屋根の面積や勾配、補強内容によって異なりますが、一般的には5日〜10日程度が目安です。雨天が続くと延びる可能性もあります。
Q. 今の瓦を使いながら耐震補強できますか?
A. 状態の良い瓦であれば再利用も可能です。ただし、割れやズレが多い場合は、防災瓦への葺き替えをおすすめすることもあります。
Q. 耐震補強は助成金や補助金の対象になりますか?
A. 一部の自治体では、住宅の耐震化に対して補助制度が設けられています。京都市でも「木造住宅耐震改修補助制度」などがあるため、まずは自治体の担当窓口や公式サイトで確認しましょう。
Q. 工事中の生活に支障はありますか?
A. 屋根工事は基本的に屋外作業で、室内に立ち入ることはほとんどありません。音や振動が発生する可能性はありますが、日常生活を続けていただくことは可能です。
Q. 山口板金ではどこまで対応してくれますか?
A. 点検から補強提案、見積もり、施工、アフターサポートまで一貫して対応いたします。地域密着型の職人直営店として、長く安心して暮らせる屋根づくりをお手伝いいたします。









